
|
|
求肥製「祇園坊」
|
|
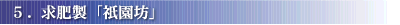
祇園精舎に遊ぶ心地〜祇園坊(干し柿)
宇治田原(京都府)では、初夏は茶畑の煙が立ち上り、晩秋には古老柿の干しすだれに、しばし、田園風景が遮られる。
いま、その干し柿に白い粉が吹き自然の甘みがわいてくるころだ。干し柿の独特の甘みは、菓子以前の保存食料として重要な産物であった。宇治田原のほかに、岐阜の大垣、広島の西条柿、徳島の貞光町、大分の耶馬渓が産地として名高く、「柿羊かん」や「巻柿」に逸品がある。
干し柿のうまみは、唐天竺は祇園精舎の苑林に遊ぶ心地がするとたたえたのか「祇園坊」の名がある。
求肥餅で干し柿の形に意匠した菓子もそういうが、“祇園坊”にふさわしくない味の土産菓子もあるから、おかしい。
祇園坊の名の本当の由来は柿の熟し色の変化を、僧侶の袈裟(けさ)の壊色(えしき)に重ねたのかもしれない。僧侶の袈裟が修業の段階によって青、黄、赤、白と移ってゆく様子を干し柿にかけたのであれば、菓子でつくる「祇園坊」の味が“青柿”であってはゆるされまい。
京菓子屋では、干し柿を切きざんで小豆あんにまぜ、織部薯蕷(おりべじょうよ)に包んでむす。
12月の茶会では、素材を水屋まで運び、茶事の進行にそって菓子職人が「柿薯蕷」を蒸し、雅客に湯気の上がる茶菓子をすすめる。薯蕷の山芋の香りとふっくらとした小豆あんに干し柿の舌ざわりと甘い渋みとが、ほどよく合ってこころあたたまるもてなしとなる。
師走は忙しい。正月には干し柿のなますでとそ(屠蘇)を祝う人も多かろう。
|
|
|
|
|
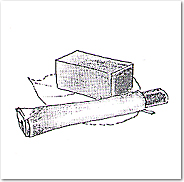
|
|
水羊かん
|
|
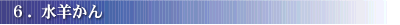
山紫水明の都を、観光パンフの中にある言葉にしてはならないと思うのだが、また、水道のくさみが気になる時期となった。
夏の生菓子は、みずみずしさをよろこびとして、冷やして食べる羊かんが多いが、中でも「水羊かん」は、練り羊かんよりも寒天や砂糖を少なめにして煮詰めずにつくるため、水分の多いのが特徴である。
その点で、とくに、水質の良否が風味を左右する。水羊かんの場合“水”が主原料であるといっても言い過ぎではない。
「水羊かん」は口に入れるとスーッと溶けるほどに柔らかく、なつかしい幼い日を思い出させ、落ち着いた気分にひたらせる。
茶菓子には、桜の葉に載せたりするが、12センチぐらいに切った青竹の中に流す「竹流し」にも涼味と風情がある。
今は一般の和菓子屋でもつくるが、元は裏千家の玄玄斎(11代)の好み菓子であった。
昔は近郊でも子供向けに、錦玉かんにカタクリ粉をまぜて半透明にしたあっさり甘味の柔らかい羊かんを、竹の底部に穴をあけて“おやつ”に与えた時代があった、という。
木陰の小川に足を洗わせ、竹笛のように切り口を吸った淡く甘い味が忘れられない、と父親が懐かしんだ。
|
|
|
|
|

|
|
くじら羊かん
|
|
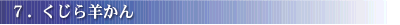
青森・浅虫温泉の名物の一つに「久慈良餅」がある。
餅といっても、搗きあげたモチの類ではない。米の粉に小麦粉を加えて、枠蒸しした外郎(ういろう)の一種で、名古屋の“ないろ”と同じように小豆あんを混ぜ、東北地方独特のクルミがいれてある。淡白な味の棹菓子で、夕涼みの折の冷たい番茶によくあう。
久慈とは、鯨の古名だという。茨城県のことを記した「常陸風土記」にその名をみる。和銅年間(713年)に書かれたもので、作者は鹿島灘で捕らえられたバカでかい魚を北方の後ろにそびえ立つ奥久慈の山々のように思えたのだろう。
古人はクジラを魚であると魚へんの漢字を当てているのがおもしろい。捕鯨する際の感じから勇ましい魚と書いて勇魚(いさな)ともいった。
“菜の花や勇魚も寄らず海暮れぬ” 蕪村
クジラの皮と脂肪層との黒と白が重なっているのに似ているところからクジラ帯(昼夜帯)があるが、羊かんも黒砂糖入りの羊かんと卵白の泡(ムース)羊かんを重ねて「くじら羊かん」をつくる。
せめて残暑の厳しいとき、青磁の器に盛られた「くじら羊かん」で、南氷洋の寒さでも想像したい。
|
|
|
写真は、京菓子協同組合青年部結成20週年誌より掲載。
|
当ページに掲載されている情報・画像を、無断で転用・複製する事を禁じます。
|

