|
|
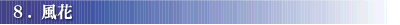
山陰や北陸方面を走る道路には“ゲリラ雪に注意”の標識がたっているのをよくみかける。
ゲリラ(遊撃)は予期しない戦いだから、ゲリラ雪などといわれていると、晴天下であっても、いつ襲われるか心配になる。だから、その地域に入る前に、流れ雪が車のフロントガラスにつかないか注意することにしている。
風上の降雪地から風に送られて飛来してくる流れ雪というより、「風花(かざばな)」という方が語感は美しい。
真っ白の薯蕷(じょうよ)に“六花(むつはな)”とこれも美しく呼ぶ雪の結晶を焼き印でデザインする茶菓子を「風花」という。
秋に収穫した新米を粉に挽き、香り高い新の山芋をすって蒸しあげた薯蕷ほど、今の時期うまい菓子はない。
しかし、市井に出回る薯蕷は、せっかくの香り高い芋の味を消し去るように“皮”が薄く、甘味が強い。往年の茶人は、自然味を大切にしたから、砂糖の少ない山芋の多い薯蕷を求めた。芋の多い薯蕷は柔らかいから、極端にいうと、つばの広い帽子のように座布団を敷いたような形に蒸しあげる。それを好んで注文される方もあった。
冷ややかな冬の茶室に、水屋で蒸しあげた薯蕷の湯気と芳香が漂う。「風花」をおもわす雪輪の濃淡も、景色の一つである。 |
|
|
|
|
|
|
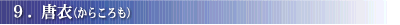
いくら教わっても、毎年この頃になると話題になり、区別ができないのが、「あやめ、菖蒲(しょうぶ)、杜若(かきつばた)」である。謡曲ですら“似たりやにたり花あやめ杜若”と謡うのだから、三者を混同しているところに話題も生まれ、人の和合もあるのかもしれない。そう考えると社交性のある花といえそうだ。
例えば五月の茶席菓子としてかきつばたをアレンジした「唐衣」がよくつかわれるが、その菓子をつくった人が、かきつばたとあやめの区別を心得ているかどうかだ。ただ先人の意匠を真似ているだけだとしたら、これこそ、“似たりやにたり、花あやめ杜若”と皮肉るしかない。
第一に、かきつばたが何ゆえに、中国服を意味する「唐衣」なのか。唐衣は“・・・着つつ”にかかる枕詞(まくらことば)だから、伊勢物語第八話の和歌を引き出し、三河の八ツ橋の「かきつばた」を連想さすのだろうか。それとも、身ごろを深くあわせて着る「唐衣」(能では長絹)の着方と茶菓子の意匠が似ているからか。
ともかくも、「唐衣」は、ウイロウやこなし製の生地を紫色に染めて、五ミリの厚さにのばし、四角に切って中央にあんを置き、番傘の先についている油紙のような容量に折り畳んで仕上げる。
からころも きつつなれにし つましあれば
はるばる来ぬる たびをしぞ思ふ (業平) |
|
|
|
|
|
|
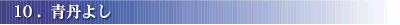
底深く“平城京”の地層に引き込むように走る近鉄の地下駅に降り立つと、いにしえの奈良の都の香りが、ある空間から漂うように感じるのは不思議である。
万葉集に「青丹よし奈良の都は咲く花のにほふがごとく今さかりなり」があるが、千代の舎竹村でつくる「青丹よし」という干菓子も花のにおうがごとく春らしい菓子だ。
緑と紅の二種につくった短冊型の薄い落雁菓子であるが白雲を表す粉砂糖を斜めに二本かけてあるのも、風雅で品よくおもえる。
古くは真砂糖(まさごとう)といっていて白色のままで売っていたものを、享和(1800年)のころ法隆寺中宮の有栖川宮に献上したおり、非常に気に入られて、色は淡青と淡紅の二色に、銘を奈良のまくらことば「青丹よし」と命名されたと伝える。いま、菓子の表面に白いカスリ模様をつけるのも、昔の真砂糖の白色を忘れないためともいう。
原料には、和三盆糖と寒梅粉をまぜ、押し固めて短冊型に切ったものが、見るからに美しく風味も淡白な茶菓子である。
いにしえの奈良の都には、春日神社にみられる青丹いろで充満していたのであろう。それとも、青丹衣の僧のことか。青丹いろの土を発掘したことからか。「青丹よし奈良の都・・・」と続くのは。 |
|
|
写真は、京菓子協同組合青年部結成20週年誌より掲載。
|
当ページに掲載されている情報・画像を、無断で転用・複製する事を禁じます。 |

