|
|
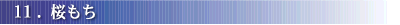
芳ばしい“春の香り”
手元に材料屋が運んできたままの桜の葉がある。塩漬け汁に沈んだその桜の葉を取り出すのが、私は好きだ。幼いころ、あせもの予防とかで、桃の葉を浮かべて入った行水の思い出と同じような芳ばしい香りがするからだろうか。
桜もちは、花だよりとは直接には関係のない春のもちだが、しかし、花だよりが新聞紙上を賑わすところが“しゅん”といえる茶菓子である。
桜もちは、桜の葉でもち飯を包んだので、そう呼んだ。桜の花が咲くころはまだ葉はない。葉を塩漬けにするのは夏である。産地は南伊豆一帯、大島のものが良質とされている。
しかし、桜もちというだけあって、花の名所が名物になっている。東京・向島の長命寺、島根・松江公園、広島・厳島の紅葉谷公園、奈良・吉野山、京都・嵐山など。
桜もちには、もち菓子に属するものと、鉄板で焼いた二種がある。小麦粉で焼いて菓子風に作るのが関東で、道明寺糒(ほしいい)であんを包んだのが関西風である。
道明寺でつくったものは、粘りがあって桜の葉がつきやすく、たべるときに葉がとれにくいことがある。そんなとき、桜の葉のままたべてもよいのかと質問を受けるが、私はすすめない。桜の葉は柏や柿の葉と同じように、受け皿(容器)だと考えたい。
茶席で道明寺製の桜餅を使うなら、桜の葉は水屋で巻いてほしい。菓子屋が巻いてきたままを茶菓子にするから客が一苦労することになる。ひと手間かけるのが席主の心得であろう。
夜桜見物に桜もちを買って、ぶらぶら下げて帰ったのは、もう、昔の風物詩か。 |
|
|
|
|
|
|
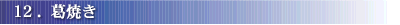
「葛」は季節では、秋の項に入っている。
葛の葉が秋風に裏返り、時雨に色づくから“恨み”の枕詞にもなる。また葛の花を秋の七草に数えたのは山上憶良だというから、葛を“秋”の季語と理解できるが、なぜ、晩秋から二月頃までの発芽期前に掘り採ってさらす「葛粉でんぷん」を“夏”の季語としているのだろう。
一つに葛は、わらびや、かたくりや、寒天や粉ゼラチンとは一味違った風味と軟らかさ、独特の香りがあって、その肌ざわりが夏菓子にピッタリの涼味と感覚を与えてくれるからかもしれない。
しかし、葛製の夏菓子の中には彩りが「夏らしくない」感じのものもある。知らない人なら“六万焼き”?と見まごうような見栄えのしない、黒っぽい四角な羊羹風。
その銘「葛焼き」は、官休庵の4代・直斎(1725−87)の好み菓子で、当時は水溶きした葛粉に黒砂糖と小豆のこしあんを混ぜて煮固めたものを、無造作に杓子で取り、鉄板で両面を焼いた茶味ある菓子であったという。
現在の「葛焼き」は 、混ぜ合わせた素材の2分の1を煮上げ、残りの生地とあわせて枠蒸しにして、冷めたものを鉄板で六方に焼き目をつけている。
焼き方には各店の特徴がでるが、サラッとした葛菓子である。 |
|
|
|
|
|
|
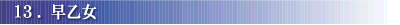
昨年は冷夏で、稲作に大きな被害を受け、ついに、カルフォルニア米をはじめ、中国やタイからも緊急輸入をしなくてはならなくなった。あげくは、米の自由貿易にも道を開く結果ともなり、今年の3月からは、主食米に70%も輸入米を混ぜざるを得なくなった。「田植えをしたが実らず」は、昨年だけの悪夢となってほしいが、さて、どうだろうか。「早苗きんとん」や「早乙女」の菓名は、“秋の豊作を祈る菓子”として、登場するとは、近年思ってもみなかった。
さて、早乙女とは、男を田人(たうど)というのに対して田植えをする女性をいうが、乙女を強調する為の接頭語の“早”の字には、神稲の意味が含まれているという。早苗も同じである。
五月の末から六月の初旬ごろ「早乙女」の銘で、すげ笠と赤襷(あかだすき)にかたどった茶菓子を作る。
すげ笠は、落雁製の型押しでもつくるが、ここでは三笠風に仕上げるものを紹介したい。
卵と砂糖をよくかくはんした中に、小麦粉と絣粉を混ぜ合わせて、平鍋(鉄板)で焼いた皮に、早苗を表すみどり色のこしあんを挟み入れ、仕上げに焼きコテでスゲ笠の編み目をつけた菓子である。
赤襷は、紅白の有平糖をねじってつくるが、赤く染めた生砂糖(きざとう)を輪に結んで、早乙女のかいがいしく立ち働く姿を表す。
早乙女が、一列にうちそろって田を植える風景を思い出さないと、この茶菓子の情緒は生きてこないかもしれないが、今のようにコンバイン化が常識になった田植え風景にとって、古来からの詩歌諷詠の世界が和菓子の意匠に残っているのも、よいのではないかと思う。
早乙女の五月雨髪や田植笠 (芭蕉) |
|
|
写真は、京菓子協同組合青年部結成20週年誌より掲載。
|
当ページに掲載されている情報・画像を、無断で転用・複製する事を禁じます。 |

